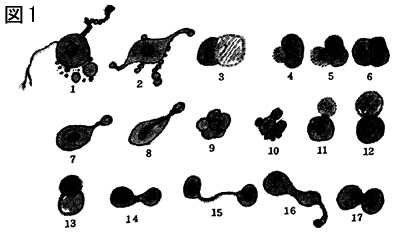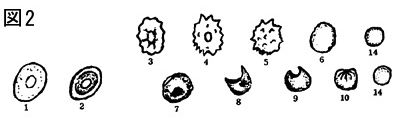2019年07月18日
定説では説明できない、恒温動物が体温を維持する仕組み
スミルノフ物理学派の佐野千遥氏は次のように指摘している。「現代西洋医学は、人体が一日に必要とするエネルギー量を食事から摂取する2300~2500kcalだけと考えているが、人間の体は例えば室温6℃の中で体温を36℃に保つ為だけでも57500~62500kcalが必要。このエネルギーはどこで生み出されているのか、現代科学は説明できない。」
とりわけ、恒温動物(哺乳類・鳥類)はどのようにして、体温を維持しているのか?
まず、生物学の定説はどうなっているのか?
結論から言えば、よくわかっていないという現状らしい。京大化学研究所梅田教授講演「地球の体温、私の体温」
比較的有力とされている説は、次のようものである。東邦大学理学部生物学科「体温はなぜ37℃なのか」から引用。
--------------------------------------------------
外部の熱源に頼って体温を上げる変温性の動物から、体内の熱生産によって高い体温を恒常的に維持する内温生への進化に関する最も信憑性の高い説明は、1979年にアメリカのベネットとルーベンによって提唱された。体温を高く維持すること自体よりも、まずは有酸素呼吸能を高めて運動機能を向上(スピードと持久力)させることに対して自然選択が作用する、このような自然選択によって上昇した最大代謝率(有酸素能)が基礎代謝率を引き上げ、体温維持の熱生産を発達させる、というもの。
しかし、体温を高く保つためにはエネルギーが必要で、哺乳類は、食物を異化する際に生じるエネルギーを熱源として体温を維持するために、大量の食物を摂取している。一方、爬虫類は、食物から熱を得る割合が少ない代わりに、太陽に直接体をさらして(日光浴)体温を上げる。例えば、同じ体重(1kg)のネズミとトカゲは活動時にほぼ同じ体温(37℃)を保っていますが、そのために、1時間当たりの消費エネルギーは、ネズミ(約2400キロカロリー)が、トカゲ(540キロカロリー)の4倍になる。
高い運動能力(スピードと持久力)は、筋収縮にエネルギーを提供するATP(アデノシン三リン酸)の高い供給能によって支えられているが、それを可能にするのがミトコンドリアの酸素呼吸である。ブドウ糖1モルの酸化によって、36モルのATPが生産される。
オーストラリアのハルバートとエルスらは、哺乳類のミトコンドリアはATP生産、熱生産の面で爬虫類よりも性能が良いのかどうか、もしミトコンドリアの性能に差がなかったら、哺乳類の細胞にはミトコンドリアがより多く含まれているのかどうかを調べた。
哺乳類が爬虫類よりも優れたミトコンドリアを持っているのではなくて、哺乳類はその内臓(肝臓や心臓)に爬虫類の5倍以上の密度でミトコンドリアを持っているとのこと。さらに肝心な点は、 筋細胞のミトコンドリアの密度は哺乳類と爬虫類の間で差がなかったという点。筋肉を構成する細胞の大半は筋繊維で占められているが、筋細胞にミトコンドリアを詰め込もうとすると、スペースに限りがあるため、筋繊維の量を減らさなければならない。哺乳類たちは、高い運動能力のために必要なATPを筋肉内で生産するのではなく、内臓の細胞に詰め込んだミトコンドリアによってまかなうように設計されてきた。要するに、内温性動物におけるスピードと持久力を担うATP生産と体内での熱生産は、内臓に増やされたミトコンドリアが担当し、強い心肺機能を使って血流を通じて全身に分配している、という説である。
-------------------------------------------------
つまり、哺乳類が恒温体温を維持しているのは、①変温動物(爬虫類)よりも大量の食物を摂取する、②内臓に爬虫類の5倍の密度でミトコンドリアを持っているということだが、この説明では佐野千遥氏の指摘に対する答にはなっていない。
つまり、体温36度を保つには6万キロカロリー:食物摂取0.25万キロカロリーで、そこには24倍もの差があるからである。
- posted by KIDA-G at : 2019年07月18日 | コメント (0件)| トラックバック (0)